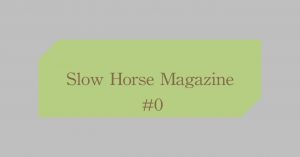競走馬故障の原因は馬場ではない。
挨拶と論点整理
初めまして、群青と申します!よろしくお願いします。The letter、初投稿です。競馬に関する些細な疑問からあまり知られていないような事柄を共に学べていけたら、と思っています!
「Slow Horse Magazine🏇」を始めたきっかけに関して詳細はこちらで語っておりますのでご覧いただけますと幸いです(^^)
馬場と競走馬の関係について今回は語っていく。
巷では「高速馬場は馬の脚に悪い!」などといった声で溢れている。トランポリン馬場と呼ばれ、スピードが出過ぎる馬場の特性に関して良いイメージを持っていないファンも多いだろう。そこで、今回はJRAの方針やラップタイムなどのデータをもとに考察していきたい。
競走馬の故障が相次いでいる
ここ数日、クラシックへ出走した馬の故障報告が相次いでいる。桜花賞・オークスの2冠を果たした”スターズオンアース”、皐月賞馬ジオグラフなどだ。その他、牡馬クラシックで連続2着のイクイノックス、NHKマイル好走のマテンロウレオ、そして天皇賞・春で一騒ぎがあったシルヴァーソニックも挙げられる。
😢故障馬リスト

🐴スターズオンアース
骨折(全治3ヶ月)
🐴ジオグリフ
骨折(全治3ヶ月)
🐴マテンロウレオ
骨折(休養期間未定)
🐴シルヴァーソニック
骨膜(全治3ヶ月)
本当に東京のスピード馬場激走が負担なのか🤔🤔🤔
東京競馬場の馬場整備はすごいと思うけどね〜。
馬場への懸念の声とJRAの方針
時計が出過ぎる「高速馬場」に対しては、メディアをはじめとして多方面で評判が悪い。馬の能力以上の時計が出ると競走馬の脚や身体に過度の負担がかかると思われていたり、コンクリートの上のような硬い馬場だからこそ速い時計が出ると信じられているからだ。
しかし、ここではスピードの出る高速馬場が馬の故障につながる直接的な要因である、ということに関して明確に否定したい!というのも、走破時計と馬場の硬さに関して明確に関係はないからだ。現に、芝よりも時計がかかるダートの方が1.3倍ほど故障率が高いことがわかっている。
馬場のクッション性と走破時計
日本競馬は早い時計というのが一つ、大きな特徴的である。実際、アーモンドアイがジャパンカップで出した2分20秒の記録は世界レコードであり、今年の日本ダービーではダービーレコードとなる2分21秒9を記録している。この早い時計の決着になる馬場要因を「高速馬場」と呼び競走馬の負担になるという声が溢れている。というのも、馬場の硬直化による高速化で脚への負担が騒がれているからだ。
しかし、以下のグラフを見れば、馬場は1995年から軟化しているのに対し、走破タイムは右肩上がりなことがわかる。
つまり、早いタイム決着の最大要因が馬場によるものではなく、馬の能力であることがわかる。

(出典:JRA)
(※馬場に関しては詳細な情報をまとめ記事化します)
「柔らかい馬場」を目指して
日本における馬場の方針は「均一性」・「平坦性」・「クッション性」の3つがポイントである。
この方針は各競馬場で共通しており、安心安全な馬場状態を目指している。
-
均一性均一性とは端的に言えば、レースにおいてどんな進路をとっても有利不利が出ない状態や部分的に悪い箇所が発生しないような状態のことである。
-
平坦性平坦性とは名の通り、馬場に凹凸が存在しない状態のことである。降雨やレース開催日終盤において凹凸が存在していた場合、馬の足に思わぬ形で引っかかり、大きなアクシデントに見舞われる可能性を孕んでいる。
-
クッション性クッション性とは馬が着地の際、負担を受け流す柔らかい馬場状態のことである。東京競馬場をはじめ日本の競馬場が「トランポリン馬場」と呼ばれている訳はこのためである。近年では、技術進化に伴い、平坦性を人力以外で賄える範囲が広がり、クッション性に比重を置いた馬場づくりがなされている。
競走馬のアスリート化
では、なぜ故障が増えているのだろか?筆者は競走馬のアスリート化にあると考えている。近代競馬では競馬に対する科学的アプローチも進んでおり、例えば、ミオスタチンなどの遺伝子情報から馬の適正距離がわかるようになってきた。
ミオスタチンとは「筋肉量の増減」を制御する因子のことで、この因子から競走馬の距離適性を検査する手法をアイルランドのエクイノム社が2010年に開発した。ミオスタチンにはC/C型(短距離型)、C/T型(中距離型)、T/T型(長距離型)の3タイプに分類され、13年に🇬🇧ダービーで1番人気ドーンアプローチ(C/C型)が惨敗したことで知られるようになった。ドーンアプローチの調教師ボルジャー氏はエクイノム社設立に大きく関わっており、出走前からミオスタチンの検査で短距離型だと診断されており、皮肉にもその結果通りになった。
その他にも、調教や放牧の休養パターンなどといったノウハウの蓄積など一昔前と比較して進んだことは間違いがない。そのおかげもあり、競走馬の能力は格段と向上した。一方で高い能力の発揮と引き換えに体への負担は大きくなるという宿命を背負うことになったのかもしれない。
終わりに~故障後のパフォーマンスについて~
読者が最も気にする点として故障後の馬の能力は下がるのか?というところだろう。競馬予想をする際にも「長期休養明け」という文言があれば、割引きたくなる気持ちもわかるが、JRAでは骨折部位による競走能力への影響は統計が取られており「第1指骨」の骨折では競走復帰率59%、平均休養期間265日。復帰した場合、獲得賞金や複勝率は罹患前から低下傾向なし、という報告がなされており、心配する必要はなさそうである。
-
スターズオンアース 両前足の第1指骨の骨折
-
両前足の第1指骨の骨折
-
ジオグリフ 右前足の第1指骨の骨折
-
右前足の第1指骨の骨折
お願い
💡 この記事🗞への返信、SNSでの紹介・拡散など、大歓迎です✌️書き続ける上で励みになります。楽しみにお待ちしております🙏
登録してくれると、なお嬉しいです!
すでに登録済みの方は こちら